ワタシ自身が子どものころ「すぐやらない人」で損をしてきました。
しかし、就職して仕事を片っ端から”やり忘れる”というとんでもない新人だったワタシは、「とにかく自分は忘れやすい。だから忘れないようにすぐやるようにしよう!」と数えきれない大失敗の後で肝に銘じました。
ただ忘れないために始めた習慣。
しかしそれは、劇的にワタシの人生を変えました。
「本当はできる自分でありたかった」というつらい過去は、「とにかくちょっとでもいいからすぐやっておく」の習慣によって、嫌な記憶であるど強いばねになってくれました。
「すぐやる」スキル、最強です。
著者は小学生の時、学年で1番の肥満児でした。
スポーツもダメ。
たくさんの塾を転々とするも、学年で一番成績が悪かったそうです。
その劣等感を引きずった挙句、高校1年生の全国模試で30台をとり、ついには新聞沙汰の事件まで起こして警察や裁判所のお世話にまでなりました。
どうやってもうまくいかないと悩む日々の中、ビジネス書を読んで気づいたのです。
成功している人、生産性の高い人は、「行動が早い」ということ。
行動を早めたことがきっかけになり、著者は変わっていきました。
今回、「すぐやる人」になるためには次のことを紹介しています
・頭の中を空っぽにする
・明日を疑う
・考えるために行動する
・9000回の負けを知っている
・目の前のことに集中する
・自分とアポを取る
・1センチだけかじる
・毎日カバンを空っぽにする

実際にはすぐに行動にうつすのは難しいことです。
実は誰でもそうなのです。
そして、「やらなきゃ」という思いの裏側にあるホンネがあります。
「本当はやりたくない」。
では、すぐできる人というのもいます。
彼らは、どうしているのでしょう?
実は彼らは気合いや意志力だけで、自分を動かしているのではありません。
「すぐやる人」は仕組みで自分を動かしています。
著者が考える、すぐやる方程式は
意志×環境×感情
です。
すぐやってしまう環境を作り、すぐやるための感情をつくり出すことで、私たちも「すぐやる人」になることができます。
すぐやる人は頭の中を空っぽにし、やれない人は頭の中で処理しようとする
スマホやタブレットが便利になりましたが、「すぐやる人」は、なんでもデジタルツールでこなそうとは考えません。
アナログツールとデジタルツールを上手に使い分けます。
アイデアは紙に落とします。
結局デジタルツールを見ると、余計なたくさんの情報が入りすぎるのは、あなたも経験していると思います。
情報が多ければ、脳内のワーキングメモリに負荷がかかります。
するとあなたの脳の処理速度が落ちます。
「すぐやる人」は、特に集中しなければならない時は頭の中にあることを紙に書き出しています。
書き出しておけば、ひとつのタスクが終わった段階で、また別のタスクについて考えることができますので、ひとつのタスクに集中します。
一方、「やれない人」は、頭の力を信じすぎているので、頭の中で解決しようとします。
紙に書き出すのは時間がかかるように思いますが、書き出すことで物事が整理されます。
まずは頭に浮かぶことをどんどん書き出していきましょう。
すぐやる人は明日を疑い、やれない人は明日を信じる
モチベーションとは魚のようなものです。
獲れたてが一番おいしいのと同じで、モチベーションにも鮮度があります。
「やりたい!」と思った瞬間がモチベーションの鮮度のピークです。
つまり、このブログを読んで「これ、やってみようかな」と思った瞬間が一番やる気が高いわけです。
これを放っておくとどうなるかは、あなたもご存知の通り。
「すぐやる人」は、未来を信じません。
「明日から」「いつか」がモチベーションの鮮度を奪っていくことを知っているからです。そして、その「いつか」はやってこないと思っているのです。
「すぐやる人」は、すぐやることでモチベーションを高めることができると知っています。
「ツァイガルニック効果」というものがあります。
「人間は達成できなかった物事や中断・停滞している物事に対して、より強い記憶や印象を持つ」というものです。
小さな一歩でもアクションを起こすことで、「やり残し感」のようなものが記憶に残り、「完成させたい」という欲求を沸き立たせるのです。
すぐやる人は考えるために行動し、やれない人は行動するために考える
大切なのは、考えるためにまずアクションを起こすことです。
「やれない人」は、「ああだ、こうだ」と考えて、理屈を言うだけで何も行動しません。
もちろん決断し、行動を起こすことには様々なリスクが伴います。
だからこそ、考えるために、まず行動しましょう。
大きく動く必要はありません。
小さく動き、軽い気持ちで試してみましょう。
つまりPDCAをごく小さなDoから始めてみることです。
あなたが小さな初動(Do)を起こす。
→すると何かしらの反応が返ってくるので、振り返りをする(Chack)。
→それから改善策を練る(Action)。
心理学の観点からも、これは非常に効果的です。
行動することで、現実の壁から何かしらの反応が返ってきます。
このフィードバックこそが最強のモチベーションを作ることが、多数の研究からわかっています。
すぐやる人は9000回の負けを知り、やれない人は全勝を目指す
「僕はこれまで9000本以上のシュートを外してきた。
これまで300試合近くに負けてきた。
決勝シュートを任されながら、外したことが26回ある。
人生で何度も何度も失敗してきた。
だからこそ、こうして成功しているんだ」
これはあの有名なマイケル・ジョーダンの名言です。
「すぐやる人」はリスクテイカーです。
理すっくを感じながらも、1つひとつ目の前の課題と真摯に向き合い、チャレンジします。
シュートは打たなければ入らないのです。
エジソンは電球を発明したときに
「私は失敗したことが無い。
ただ1万通りの、うまくいかない方法を見つけただけだ」
と言った話はあまりに有名ですが、どの時代にも成功者はみな失敗を語ります。
すぐやる人は目の前のことに集中し、やれない人は結果ばかりを気にする
「もしも今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは 本当に自分のやりたいことだろうか?」
これはステーブ・ジョブズが残した名言ですが、「すぐやる人」というのは「今」と言うものを、過去よりも未来よりも大切にしています。
人生は今、この瞬間に目の前で起きていることでしかなく、誰にも未来は保証されていないからです。
だから、目の前のことに全力を注ぎます。
そして、成果は自分で決めることができません。
成功するかの要素は、相手も環境もあり、複雑に絡み合っています。
もちろん、過去にとらわれるのは、よくありません。
過去の栄光にすがってしまうのは、今の自分がそれ以上のものではないからです。
つまり、現状に満足できていない証です。
そして私たちは、未来を語ることによって、生きる勇気が湧いてきます。
しかし、遠くばかりを見ていると足元の小石につまずいてしまいます。
未来を描きながら、今この瞬間に意識を向けること、目の前のリアルに注目できるかが重要なのです。
すぐやる人は自分ともアポをとり、やれない人は他人とだけアポをとる
あなたはスケジュール帳に何を書いていますか?
もちろん仕事の予定や友達との予定はスケジュール帳で管理している人はとても多いでしょう。
「やれない人」は、ここで完結してしまいます。
あなた自身との約束もスケジュールに落とし込んでいますか?
著者は面倒くさがりと自任しているので、しっかりと自分の予定を明確にしておかないと、ズルズルと怠けてしまうそうです。
他人との約束は信用問題だから守るとしても、自分との約束は簡単に言い訳ができてしまうからです。
著者は日曜の夜に1週間の予定を作成しますが、仕事以外の時間帯を、緊急性は低くても重要性の高いものを確保しています。
自分を磨くためのインプットの時間を徹底して確保すること。
たとえば、読書をする、英語の勉強をする、ジムへ行く、会いたい人に会う、整理整頓をする、などの自己投資の時間。
これをスケジュール帳に落とし込んでおくことを習慣づけると、今よりももっと時間への意識を高めることができます。
そして、あなたは時間をコントロールできているという感覚を持つことができます。
それは確かなモチベーションを生みます。
スケジュール通りに物事が進んでいるときは、あなたの内側からエネルギーがみなぎってくる感覚を覚えた経験があると思います。
忙しくて計画通りに行くか不安でも、とにかく計画だけは立ててみましょう。
計画を立てることで、なぜ計画通りにならなかったのかを分析することができます。
「やらなければならないことがあったのに、ついつい誘いに乗ってしまった」ということを客観的に把握することで、別の時間にそれを埋め合わせる意識が高まって、状況に流されてしまう可能性は低くなります。
すぐやる人は、まず1センチだけかじり、やれない人はあとで全部食べようとする
私たちの日々の行動を分類する方法はいろいろありますが、中でも「自分で決めたこと」と「他人から依頼されたこと」の2つに行動を大別することは、「すぐやる」か「やらない」かを考えるときに重要になってきます。
自分で決めたことは当然、当事者意識がありますが、他人からの依頼はそもそも当事者意識がないものだから、後回しにしやすくなります。
だから、物事を能動的に進めるには、自分に当事者意識を持たせることが重要なのです。
そのためには、依頼を引き受けたのならば、最初にちょっとした出だしを舵っておくことで当事者意識を持つことができます。
今やっているタスクを中断することになるので、中途半端になることを懸念するかもしれません。
しかし、先ほどもありました「ツァイガルニック効果」が働いて、未完了の課題の記憶は頭に残ります。
ドラマはいつも「ここからが気になる!」というところで「次に続く」となります。
だから、依頼を引き受けたら、少し手を止めて、依頼されたものを少しだけ手を付けることをお勧めします。
どういう計画なら、その依頼を成し遂げられるか、スケジュールを立ててみることでもいいでしょう。
他人を巻き込むなら、早速連絡をいれてみるのも手です。
逆算してあなたのアクションを具体的に想定して、疑問点を洗い出してもいいでしょう。
疑問点は早めに質問して解消しておかないと行動に具体性が出ません。
モヤモヤしたままだと、自分でコントロールできている感覚が減ってしまい、当事者意識も薄くなります。
しかし、そのままだらだらと続けてしまうと、中途半端なマルチタスクになりかねません。
5分以内と時間を区切って手を付けるようにします。
時間制限を持たないとだらだらとなりますので、ここでも時間制限を設けることで瞬発力と集中力を高めたいものです。
「すぐやる人」は、他人からの依頼でも、自分に当事者意識を持たせることを考えています。
だから彼らは相手の期待値を少し上回り、信頼を勝ち取り、好循環を回します。
以来を引き受けたら、出だしが重要です。
5分以内にできることを探し、少し手を付けておくだけと言った工夫で大きな違いを生み出していきましょう。
すぐやる人は毎日カバンを空っぽにし、やれない人は入れっぱなしにする
仕事や学校から帰ったら、カバンはどうしていますか?
ここにも「すぐやる人」と「やれない人」の差が現れます。
「すぐやる人」はカバンの中を毎日整理する習慣を持っています。
なぜなら、先延ばしにしてしまう原因のひとつは、モノがきちんと整頓されていないことにあるからです。
往々にして、ものが整理されていない状態ならば、頭の中も整理されていない状態であるといっても、過言ではありません。
どこに何があるのかをはっきりと把握できていないため、もの探しに多くの時間を使っている人も少なくありません。
せっかく「よし、やるぞ!」と思っても、一歩踏み出すまでに時間がかかってしまうと、「また明日でいいや」となることがありませんか?
ワタシはよくあります!
「すぐやる人」は帰宅したら毎日、書類や荷物をカバンの中から出し、必要なものはどこの定位置に戻すかを決めています。
そうすることで、頭の中もすっきり整理された状態に保つことができるのです。

今回のおさらいです
・アナログも使って、頭の中を空っぽにする
・モチベーションは生もの(すぐ鮮度が落ちるもの)だと心得る
・小さく行動してみてからPDCAを回して考える
・結果より目の前に集中する
・週末に自分が本当にやりたいことをスケジュール帳に落とし込む
・依頼されたら、その瞬間5分限定で動き出しておく
・帰ったらカバンは空っぽにする
今週もお疲れさまでした。
ゆっくり休んでくださいね。
では、また。
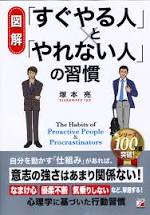
・